目次
1.はじめに:なぜ今、ビルメンテ業者に石綿知識が必要なのか?
近年、石綿(アスベスト)に対する社会的な関心が高まっています。特に建物の維持管理に関わるビルメンテナンス業者にとっては、知らぬ間に石綿に接触してしまうリスクが現実のものとなってきました。
2022年の法改正により、石綿の有無調査や作業記録の義務化(を含む作業基準)が強化されたことを受け、清掃や点検といった日常業務の中でも、石綿の存在を意識した行動が求められています。石綿は目に見えない微細な繊維であり、建材の奥に潜んでいるため「見えないリスク」として警戒が必要です。
2.石綿(アスベスト)とは?ビルメンテ業務に潜むリスク
石綿は、耐火性・断熱性・絶縁性に優れた素材として、1970〜1990年代を中心に多くの建物で使用されました。現在は禁止されているものの、古い建物には依然として多くの石綿含有建材が残っています。
<含まれている可能性がある場所・設備例>
• 天井や壁のけい酸カルシウム板、スレート板
• 吹付け耐火材(鉄骨梁・ダクト)(天井スラブに変更:ダクトに吹付耐火材は?)
• 床のビニールタイルや接着剤
• 配管の断熱材、フランジパッキン


【清掃・点検時の粉じん暴露リスク】
経年劣化や破損により石綿が露出している場合、清掃作業などで微細な繊維が空気中に舞い上がることがあります。呼吸器に吸い込むことで、中皮腫や肺がんといった健康被害の原因になることから、作業環境と手順の見直しが必要です。
3.業務中に石綿と接触する具体的なシーンとは?
石綿のリスクは、解体や大規模改修だけに限りません。日常的なメンテナンス作業の中にも潜んでいます。
- エアコンフィルター清掃
天井裏のダクトや断熱材が石綿含有の可能性があり、点検口を開けるだけで粉じんが飛散する恐れがあります。 - ボイラー室・機械室の点検
高温機器まわりの耐火材・断熱材に石綿が使用されている例が多く、特に築年数が古い建物では注意が必要です。 - 古いタイルや配管まわりの清掃
床のビニールタイルや、壁面の巾木など、一見すると無害に見える場所に石綿が使われているケースもあります。


4.ビルメンテナンス業者がとるべき5つの安全対策
- 作業前の事前調査の有無確認
建物所有者や元請業者に対し、「石綿調査済か」「含有建材の位置は把握されているか」を確認しましょう。 - PPE(個人用保護具)の使用
N95以上のマスク、防護服、手袋、ゴーグルなどを必要に応じて装着し、曝露を最小限に抑えます。(N95は医療感染予防 粉じんにはDS2以上の方が適当では) - 作業記録と報告の徹底
作業日、場所、気づいた異常、破損建材の有無などを日報に記録。疑わしい場合は上長や元請に報告を。 - 石綿作業主任者との連携
現場に主任者がいる場合は指示を仰ぎ、作業前にリスクのある箇所を確認しておくと安心です。 - 緊急対応マニュアルの整備
万一、破損や飛散が起きた場合の連絡先、避難手順、封じ込め方法などを社内マニュアルとして整備しましょう。


5.万が一、石綿に接触してしまったら
【初期対応と報告の流れ】
• 作業を即中止し、現場を隔離
• 上司・管理者へ速やかに報告
• 可能なら現場写真や状況を記録
• 関係部署や建物管理者に連絡し、封じ込め・除去の判断を仰ぐ
【健康診断の必要性(定期的な石綿粉じん作業の場合は半年に1回)】
明らかな石綿暴露があった場合は、産業医や呼吸器専門医の受診を推奨します。石綿による健康被害は長期的に現れるため、年1回の健康診断で経過を観察することが重要です。
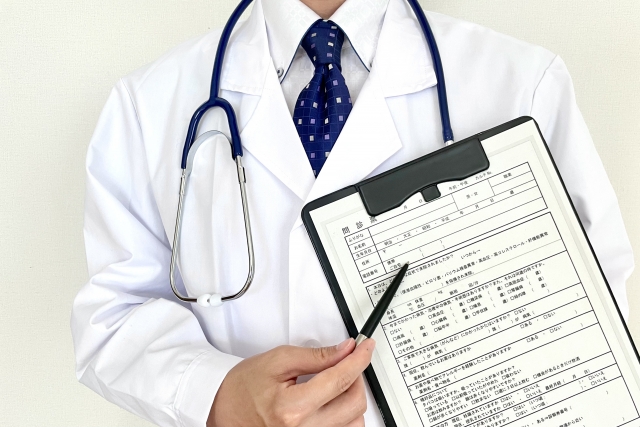

6.まとめ|法改正前に対応しておくべきこと
石綿リスクは「知っていれば防げる」ものです。
2022年の改正石綿障害予防規則(石綿則)や大気汚染防止法の強化を受け、ビルメンテ業者も他人事ではいられません。
• 自社でのマニュアル整備
• スタッフへの基礎教育
• 調査済建物リストの作成
• 作業前の確認ルーチンの確立
これらを着実に進めることで、作業者の安全と建物利用者の安心を守ることにつながります。
▼石綿調査後、簡単に報告書を作成出来るシステムもございます。是非ご覧ください。

1991年 NTT入社、その後2007年に総合解体工事業大手の株式会社前田産業に入社、解体工事業を現場から学び、その後同社常務取締役を得て、2022年株式会社metalab.を設立。 自らが経験した解体工事業の経験を活かし、人口減等の社会的課題を解体業に特化した サービス提供で業界イノベーションを推進したい思いから事業を立ち上げ、現在では解体 工事現場代理人教育や解体施工技士対策講師等も実践している。解体工事業界18年目。

コメント