工場改修のたびに繰り返す石綿調査を効率化 ― 物件管理で“社内工事部門”の負担軽減
製造業の多くは、自社工場や研究所といった大規模施設を所有しています。建物は稼働年数が長く、定期的な改修や設備更新が欠かせません。その際に必ず必要となるのが「石綿(アスベスト)調査」です。
しかし、多くの現場で繰り返し同じ問題が発生しています。改修やレイアウト変更のたびに調査をやり直し、ゼロから建材を確認し、報告書を作成する――。この非効率なサイクルは、社内工事部門や設備管理部門にとって大きな負担となっています。

■ 調査の繰り返しが生む課題
工場や研究施設を持つ企業では、以下のような課題が目立ちます。
- — 毎回の調査コストがかさむ: 同じ建屋で何度も調査が発生し、費用も時間も浪費。
- — 履歴が分散し、情報が活用できない: 過去の調査データが紙や個人の管理に留まり、次の改修時に再利用できない。
- — 属人化による手戻り: 担当者が替わると過去の履歴が活かせず、再度ゼロベース調査。
- — 品質ばらつき: 記録方法や切り分け基準が異なり、比較や管理が困難。
これでは社内工事部門が、法令対応の繰り返しに追われ、本来の「生産設備の効率化・改善」に力を注げなくなります。

■ 解決のカギは「物件管理」
こうした課題を解決するのが「物件管理機能」を備えた調査システムです。建物や工場を単位として調査データを登録・蓄積することで、次回以降の改修では既存情報を参照し、更新や追加部分だけを確認すれば済むようになります。
導入による効果
- 調査履歴の一元化:建物ごとに調査・分析結果を蓄積。工場全体のリスクを俯瞰可能。
- 調査スピードの向上:ゼロからの調査が不要になり、必要箇所の追加確認に集中。
- 調査品質の均一化:登録データを参照することで、表記や判断基準を統一。
- 設備投資計画への活用:どの棟にどのリスクが残るかを整理し、長期修繕計画に反映。

■ 工場ならではの活用シーン
たとえば、製造ラインを更新する際、建屋の一部を改修する場合を考えてみましょう。初回調査で建物全体の情報を物件管理に登録しておけば、次回以降の改修工事は対象範囲を絞り、効率よく調査を進められます。
さらに、複数工場を持つ企業であれば、各拠点の調査履歴を横断的に管理できます。これにより、設備投資の優先順位をリスクベースで判断することも可能になります。

■ 調査を「コスト」から「資産」へ
石綿調査は法令で義務付けられた対応ですが、単に“やらされる仕事”で終わらせてしまうのはもったいないことです。物件管理の仕組みを導入すれば、調査結果は将来の改修計画や投資判断を支える「資産」として活用できます。
工場改修のたびに同じ手間を繰り返すのではなく、データを積み重ねて次に活かす。そうした取り組みが、社内工事部門の負担を軽減し、発注者から信頼される企業への一歩となるはずです。
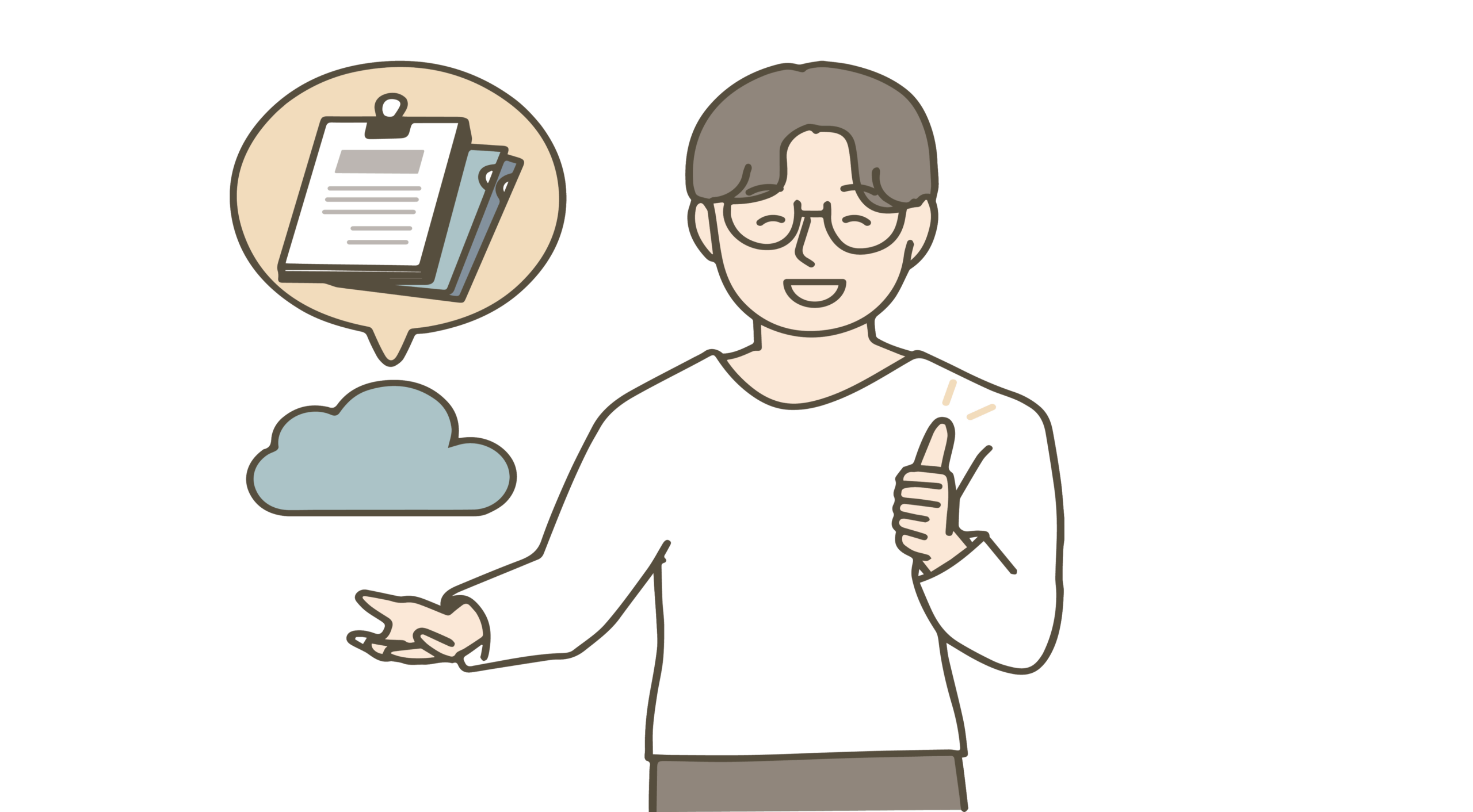
■ メタラボ石綿事前調査システム
メタラボ石綿事前調査システムなら、物件管理を中心に調査データの一元管理・CSV出力・レポート自動生成までワンストップ。工期リスクとコストを抑えつつ、品質を平準化します。



コメント